 寒暖差アレルギー
寒暖差アレルギー 寒暖差アレルギー
寒暖差アレルギー 朝、起床時に布団から出たり、室内から外に出たときに、突然鼻がむずむずして、くしゃみや鼻水が出たりすることはありませんか。秋の花粉(ブタクサ、ヨモギなど)によるアレルギー性鼻炎の可能性もありますが、今のような朝夕と日中の温度差が大きい時に見られる、寒暖差アレルギーかもしれません。医学的には、血管運動性鼻炎といって、鼻の粘膜の神経が刺激され、鼻の血管の太さが変化し、症状を引き起こすと考えられています。一種の自律神経の乱れが原因で、1日の温度差が7℃以上になると、多くなるようです。花粉症とは異なり、アレルゲンが見つからず、目がかゆくなったり、充血したりすることがなく、鼻水の色も透明でさらっとしています。一般的には、筋肉量が少ない成人女性が、自律神経の調整がうまくいかず、なりやすいといわれています。
寒暖差アレルギーの対策は、こまめに衣服を脱いだりして、極端な温度変化を体に与えないこと。マフラーや手袋、厚手の靴下などを着用して、冷たい外気に触れる部位を減らす。汗をかいた後は、すぐに拭き取ったり着替える。マスクをして鼻の粘膜を温め潤す。ぬるめのお風呂に入り、リラックスするようにする。ニンニクやショウガなどの香辛料を使った料理で、体の血行を良くするなど、自律神経のバランスを整え、温度差のない生活を心掛けることが大切です。
それでも症状が続き、日常生活に支障がある場合は、医療機関に相談をしてください。
平成25年12月 佐藤政晃
今年1月30日、厚生労働省から山口県内の成人女性が、昨年秋にマダニを介した新型のウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」で死亡したと発表がありました。報道などによると、2月には愛媛と宮崎で成人男性が1人、続いて広島で成人男性1人が、長崎では60歳男性が平成17(2005)年の秋に感染し死亡していたとのことです(3月12日現在)。
これを聞いて、マダニが媒介する感染症が今治でも過去に発生していたことを思い出しました。それはウイルスではありませんがリケッチアというウイルスと細菌の中間の大きさの病原体です。これは「日本紅斑熱」といい、愛媛県では74例の発生があり、今治保健所管内でも発生報告があります。症状は高熱、倦怠感、頭痛、悪寒と、刺し口には米粒大の赤い発疹ができるなどで、かゆみや痛みは感じません。
この症状にそっくりで、刺し口までよく似たリケッチア感染症に「ツツガムシ病」があります(聖徳太子の時代の話を思い浮かべる方もいるでしょう)。これはマダニよりもずっと小さなツツガムシというダニが媒介し発症するものです。愛媛県では9例の発症報告がありますが、そのうち3例が今治保健所管内での発症でした。この2種類のリケッチア感染症は治療法が確立していますが、放置すると重症化、死亡する例もあるので、今回見つかったウイルス感染症のSFTS
と同様にダニに咬まれない予防をすることが大切です。
予防法…SFTS と日本紅斑熱やツツガムシ病はともにダニの活動季節が危険です。春から秋に行楽で野山に入る場合、農作業でみかん山に入る場合、ときには市街地の草むらでも感染した例があったそうですので、着衣や靴を選んで肌の露出はできるだけ避けるようにしてください。帰ってから発熱などの症状があった場合は速やかに病院で受診することが必要です。なお、SFTS
については、今後の新しい情報にご注意ください
平成25年4月 井出 透
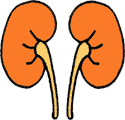 eGFR かタンパク尿か
eGFR かタンパク尿か 「先生、私の腎臓は半分しか働いてない」高血圧で治療中のAさん。少し声が震えています。その原因はeGFR です。最近、健診に導入されました。
「eGFR =推算糸球体濾過量」、日本語に訳してもさっぱりわかりません。一言でいえば、腎臓がどれだけちゃんと働いているかということです。腎臓の働きは血液の中の老廃物を水分と一緒に尿へ排泄することです。同年齢の健康な人を100%
パーセントとして表した指標がeGFR です。例えば、eGFR が70〜80なら腎臓はしっかり働いています。AさんのようにeGFR が50なら、「ちょっとさぼり気味?でも、去年と同じだからまず大丈夫」そうお話しすると、いつものAさんに戻ったようです。eGFR
は数値より経過の方が大切なのです。
今度は少々太り気味のB さん。毎年検診で血糖値が高めだといわれていましたが、今年はタンパク尿(±)のオマケがついてきました。B さんは別に驚いた様子はありません。
タンパクは血液の中の重要なエネルギー源の1つですので、尿の中に漏れ出てしまっては一大事です。たとえ腎機能が正常(eGFR =100)でも、タンパク尿が少しでもあれば腎臓に傷害(病気)があるということです。特に、糖尿病あるいは、Bさんのように糖尿病予備軍のような人のタンパク尿には警戒が必要です。Bさん少々不安になってきました。「必要に応じてお薬を使いながらしっかり治していきましょう」と声をかけると、Bさん少しほっとした様子です。
慢性腎臓病は、高血圧や糖尿病、動脈硬化などのさまざまな病気によって徐々に進行する腎臓の病気です。タンパク尿は、この忍び寄る慢性腎臓病をいち早く発見するための鋭敏な検査です。慢性腎臓病の予防や治療には、eGFR
はもちろんですが、タンパク尿の程度を把握することがより大切なのです。
平成24年11月 北見 裕
糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの作用が不足して起こる病気です。インスリンの作用が不足すると、ブドウ糖を利用できなくなり、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなります。この状態が糖尿病です。糖尿病は、大きく1型と2型に分けられますが、生活習慣病といわれているのは2型糖尿病の方で、遺伝的背景(血縁者に糖尿病患者さんがいる)に、食べすぎや運動不足など生活習慣の乱れが加わり発症します。
近年、特定健診を含めた健診が盛んに行われており、以前に比べて糖尿病も早期に見つかることが多くなりましたが、症状がほとんどないため、健診で指摘されても、医療機関を受診せず、無治療の方が多数います。平成19年の国民健康栄養調査では、糖尿病が強く疑われる方が約890万人もいましたが、その4割はほとんど治療を受けたことがないという結果でした。糖尿病は、慢性疾患といわれていますが、治療を受けず高血糖状態が続くと、合併症が進行し、膵臓のインスリン分泌力も低下する進行性の病気です。合併症には、3大合併症である神経障害、網膜症、腎症と心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化性疾患があります。合併症も、進行しないと症状が出現しないことが多く、網膜症で突然視力を失い受診される患者さんもいます。合併症のため生活の質が著しく低下し、健康寿命も短縮します。
健康で長生きするためにも、糖尿病と言われたら、早めに病院を受診し、治療を継続してください。そして、血縁者に糖尿病患者さんがいる、肥満がある、境界型と言われている場合は、定期的に検査を受けてください。
平成23年7月 小堀友恵
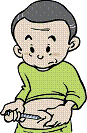 糖尿病について
糖尿病について糖尿病は血糖値が高くなる病気です。食事をすると血糖値が上がり始めますが、この時に、血糖値に反応して体内で唯一の血糖降下ホルモンであるインスリンが膵臓から分泌されて、血糖を下げるように働きます。しかし、このインスリンの分泌量が少なかったり、その作用が悪かったり(抵抗性といいます)すると、血糖値は正常な範囲まで下がらず高血糖となります。糖尿病は慢性の高血糖を主徴とする代謝疾患群であり、このインスリンの作用不足が主な病態です。わが国の糖尿病患者数はこの50年の間に約40倍増加しており、この主要な原因はライフスタイルの変化による運動不足と脂肪摂取量の増加と考えられています。日本人の糖尿病の大部分を占める2型糖尿病は家族歴と明らかに関連し、この遺伝的背景のうえに、過食、肥満、運動不足、ストレスなどの環境因子が加わり発症します。高血糖状態が長く続き、糖尿病が進行すると、特徴的な合併症(細小血管障害)を引き起こして、失明や透析導入などの原因となるばかりでなく、心筋梗塞や脳梗塞を合併して、生活の質(QOL)を著しく低下させ、健康寿命の短縮をもたらすので、その予防と早期の診断、適切な治療がとても大切です。糖尿病の治療は、まず食事療法、運動療法を中心とした生活習慣の改善が基本です。これだけでは不十分な場合には、経口血糖降下薬またはインスリンによる薬物療法の適応になります。糖尿病の早期には自覚症状がないことがほとんどなので、血縁者に糖尿病の人がいたり、最近急に太ってきた肥満の人や、ストレスの多い人、などは「リスクがある」、と考えて、定期的に検査を受けてください。
平成21年8月 真部 淳
 超音波検査(エコー)について
超音波検査(エコー)について 超音波の医学への応用は1940年代から始まり、現在のような電子スキャン法(リアルタイムで人体の断面を観察する方法)が実用化され飛躍的に進歩し、害がなく楽でよくわかる検査として、一般臨床に広く普及しています。ここでは、特殊なエコー(術中、体腔内、生検、治療)でなく、日常的にエコーでよくみられる病気についてお話しします。
健診では腹部をよくみますが、心臓、血管、泌尿器、産婦人科、甲状腺、乳腺、頚部にもよく使われます。腹部では、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓、大血管、子宮、卵巣、前立腺、膀胱などをみます。最も多いのは腎のう胞(袋)で、健診時、10人に1人はあります。胆のう結石も多く無症状でも健診でよく見つかります。腎臓、尿管の石もよくみられます。肝臓・膵臓ののう胞も時々あります。肝血管腫(良性)も時々あります。肝臓癌(原発性)は、90パーセントがウイルス性(B、C型)の肝炎、肝硬変の方から生じます。特にB、C型肝硬変の方からは年率7パーセントの高頻度で肝臓癌ができます。そのため、厳重なスクリーニング検査(エコーは3か月に1回、CTは6か月に1回など)が必要です。そうならないために、肝炎ウイルスのスクリーニング検査をされ、必要があれば専門医で、ウイルス駆除治療(インターフェロンなど)をしてください。
高齢者になると、心臓エコーをすると、半数以上に心臓弁膜症があるといわれますが、治療の必要性については専門医(循環器)にご相談ください。
また、最近は、頚部のエコーにて、血管の屈曲蛇行をみたり、IMT(血管の壁の厚さ)の計測、プラークの検索にて、直接、動脈硬化の程度を推測できす。
最後に、エコーも機種、探触子により、腹部、心臓、体表面、体腔内型などに分かれますので、各医療機関で観察可能な部位はご相談ください。
平成19年9月 西信 正男
私たちの体の約60パーセントは水分で占められていますが、この水分は、細胞の中にある細胞内液と、細胞と細胞の隙間にある細胞間隙を埋める間質液、そして血管の中にある水分とに大きく分けられます。通常、体内の水分は、この細胞内、細胞間隙、血管内の3
つの場でのバランス(割合)が一定に保たれた状態で、それぞれの場の間を行き来しながら、体に必要な酸素や栄養分、不要になった老廃物などの運搬、発汗による体温調節などの重要なはたらきを果たしています。
ところが、何らかの原因でそのバランスが崩れたとき、血管から細胞間隙に出てくる水分が増えすぎることがあります。するとその部位が膨張することになりますが、この状態がいわゆる「むくみ」になります。バランスが崩れる原因としてはさまざまなものがありますが、すべてが病気に関連するものではありません。一般的には、一時的なもので、一晩寝れば元に戻るようなものはあまり心配ないといえます。たとえば長時間の立ち仕事や歩行を続けたあとなど、夕方にのみ少し足がむくむなどがこれにあたります。月経前にむくみがみられる人もいます。
気をつけたいむくみの原因としては、心臓、腎臓、肝臓の病気があげられます。甲状腺の病気でもみられることがあります。また女性に多く見られる病気として、特発性浮腫という原因不明の病気もあります。いずれにしても、むくみが長引いたり、悪化していく場合、尿量が減る場合、急激な体重増加がみられるような場合は、病気に関連するものでないかどうか、早めに医療機関を受診することが大切です。
平成17年6月 山内 京子
亜急性甲状腺炎という病気を耳にしたことがおありでしょうか。細菌感染のために突然におこる急性甲状腺炎ほど短期間でもなく、自己免疫が原因で年単位で経過する慢性甲状腺炎ほど長期間でもないということで、その間をとって亜急性と呼んでいます。
上気道炎の症状が先行すること、数週間で自然に治まることなどからウイルス疾患だろうと考えられています。原因ウイルスとして候補はありますが、確証されていません。ウイルスに感染すると直接病気になるのではないため、家族にはうつらないと考えてかまいません。30~50歳が好発年齢で、女性が男性の5~10倍かかりやすいといわれています。先行する気道感染の後、突然に前頚部痛と発熱を認めます。痛みの程度には差がありますが、下顎から耳介後部に感じるので、耳痛や歯痛として感じることがあります。全身症状としては、倦怠感が強く、半数の人に発熱を認めます。血中に甲状腺ホルモンが漏出するので、動悸、発汗などの甲状腺中毒症の症状が見られます。
基本的には自然に治癒する病気ですので、治療は対症療法になります。数か月でほぼ正常の甲状腺組織になり機能も戻りますが、10パーセント以下の人は永続的な甲状腺機能低下症となります。主治医の先生に症状を伝えて、検査の結果を見てもらいながら治療を受けてください。
平成17年4月 三宅川 慶子
膠原病とは、血液中に自己の細胞や組織を構成する成分に反応する抗体を産生し、さまざまな臓器に炎症を起こす、一種の自己免疫疾患の総称で、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎(皮膚筋炎)、結節性多発性動脈炎、慢性関節リウマチ、リウマチ熱や、シェーグレン症候群、ベーチェット病などが含まれます。
原因は今のところ不明ですが、遺伝的素因に種々の環境因子(ウイルス感染、ストレス、紫外線、妊娠出産など)が加わり、発症するのではないかと推測されています。膠原病の多くが、厚生労働省の特定疾患(いわゆる難病)に指定されていますが、それほど珍しい病気ではありません。
診断は、典型的な症状や検査所見が揃えば難しくありませんが、そのような例はむしろ少なく、初発症状としては、微熱、全身倦怠感、口内炎、リンパ節腫脹(耳の後ろや顎の下、脇の下や足の付け根のグリグリ)、関節痛、手指のこわばり、皮疹、レイノー現象、眼や口腔内の乾燥感など、他の疾患でもよく見られる症状が中心です。また、検査所見では、蛋白尿や血尿、貧血、血沈亢進など、非特異的なもので発見されることがあります。一方、膠原病、リウマチ疾患の診断によく用いられるリウマチ因子や抗核抗体は、陽性であっても病気の存在を疑うことはできますが、確定診断はできませんので注意が必要です。
したがって、膠原病の診断は症状、検査所見などを総合して進めていく必要がありますので、先に述べたような原因不明の微熱や貧血、難治性の皮疹や口内炎、口や舌の乾き、手のこわばりや筋肉痛が持続する場合は、一度専門医を受診してください。
また、膠原病は他の自己免疫疾患、例えば橋本病(慢性甲状腺炎)、自己免疫性肝炎、自己免疫性溶血性貧血、重症筋無力症などと合併することがありますので、これらの疾患で治療中の方でも、先に述べましたような症状が出現した場合には、主治医の先生に相談されることをお勧めします。
平成16年7月 佐藤 政晃
 頭痛の種類と片頭痛、緊張型頭痛について(上)
頭痛の種類と片頭痛、緊張型頭痛について(上)「頭が痛い」といってもその原因にはいろいろあります。頭痛は大きく3種類に分類されます。まず1番目に、誰もが経験したことのあるような風邪や二日酔いからくる頭痛で、これは本人にも原因がわかり、また原因がなくなれば消失するもので心配のない頭痛です。2番目は、クモ膜下出血や脳腫瘍などを原因とする危険な頭痛です。こうした脳の病気による頭痛は、CTやMRIといった検査で診断ができます。ほかに眼科の病気で、急性緑内障に伴う強い頭痛には注意が必要です。3番目が、繰り返し強い頭痛に悩まされるのに、脳の検査をしても異常が見つからないため軽く見られてしまう事が多い慢性頭痛です。いわゆる「頭痛もち」といわれるタイプの頭痛が慢性頭痛で、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛の3つに分けられます。これらの頭痛は、それぞれ立派に1つの病気とされる、特徴のある症状を持っており、多くの場合日常生活にかなりの支障をきたしています。統計では日本人の片頭痛の有病率は人口の8.4パーセントで、定期的に医療機関に通院している人は片頭痛全体の2.7パーセントとなっています。医療機関の受診率は低いにも関わらず、日常生活支障度は相当高く、「いつも寝込む」が4パーセント、「時どき寝込む」が30パーセント、「寝込まないが支障大」が40パーセントと、約70パーセントの人が相当支障を感じていることになります。今回は、頭痛全体の話をさせていただきましたが、次回は、片頭痛の実態についてお話させていただきます。
平成15年2月 鈴木 孝
慢性頭痛の代表的なものの一つが片頭痛です。片頭痛では、頭の片側(時に両側)がズキンズキンと脈うつような激しい痛みに襲われ、こうした痛みが月に1~2回、多い人では週に1~2回発作性に起き、数時間から3日間ほど続きます。頭痛以外の症状として吐き気がしたり、実際に吐いたり、また体を動かす、音を聞く、光を見るなどで痛みがひどくなる、また前ぶれとして約10~20分間、視野にチカチカしたりギザギザした模様が広がって、物が見えにくいといった症状が出る場合もあります。片頭痛は男性にもありますが、最も多いのは30代の女性です。
片頭痛の病態はまだ不明な点が多いのですが、現時点では脳の血管が痛む頭痛であり、セロトニン受容体が重要な役割を果たしていることが確認されています。最近、片頭痛に関する、このセロトニン受容体を刺激する薬物であるスマトリプタンが片頭痛と群発頭痛に著効を示すことが発見されました。
従来片頭痛に使用されていた酒石酸エルゴタミン製剤は、人により、また発作により、効果が十分であったり不十分であったり色々でしたが、その作用機序はセロトニン受容体刺激であるが、スマトリプタンほどの選択性がないことも最近わかりました。片頭痛急性期の治療薬として、欧米ではスマトリプタンに続き同種の薬剤が数種類使用されており、最近わが国でもスマトリプタンの注射薬、経口薬が承認されています。片頭痛に悩める人の朗報になれば幸いです。
次回、緊張型頭痛の実態についてお話をさせていただいて、この頭痛の話を終わりといたします。
平成15年3月 鈴木 孝
緊張型頭痛はストレス頭痛ともいわれ、精神的あるいは身体的ストレスによって起こる頭痛です。
緊張型頭痛は持続的な頭痛で、徐々に始まり、1日中あるいは毎日続いて起こる頭痛です。頭部全体を締めつけられるような、頭全体が重く圧迫されるような不快な頭痛で、常に頭痛にとりつかれているように感じます。頭痛によく伴う症状として、目の疲れ、耳鳴り、めまい、肩こり、疲れやすさなどがあります。片頭痛が、体を動かすと頭痛がひどくなるのに対して、緊張型頭痛は、体を動かしたほうがかえって気がまぎれて頭痛が軽くなったり忘れることがあります。
緊張型頭痛を起こすストレスの原因にはいろいろあるため、自分の頭痛が緊張型頭痛だと思ったら、その原因を探してみる必要があります。
(1)精神的ストレス 緊張型頭痛の原因となるものとしては、不安、うつ状態などがあり、不眠が続くこともあります。
(2)身体的ストレス これは主として頭や首の後ろの筋肉に負担をかけ、頭痛を起こします。同時に肩こりを伴うことが少なくありません。OA作業のような不自然な姿勢の継続、うつむき加減の悪い姿勢、睡眠不足、眼精疲労、頸椎症のような首の骨の変形、そのほか多くのことが原因となります。上記の改善や、緊張した筋肉を柔らげるための軽い体操や、背筋を伸ばしたり、肩を回したりする運動、そして、補助的ではありますが、薬剤による治療などが有効です。
最後に、新しい試みとして、頭痛の種類、頻度、強度、持続時間、誘因を知り、治療計画を立てるうえでの参考となる頭痛日記というものも開発されていることをお話しして、この頭痛についての話を終わらせていただきます。
平成15年4月 鈴木 孝
 頭痛の話
頭痛の話 ペインクリニック(疼痛外来)の患者さんの中には、いわゆる“頭痛もち”の方も少なくありません。慢性の機能性頭痛と呼ばれるものがそれで、大きく三種に分類されています。
この中で片頭痛は文字通り頭のいずれか半側に生じる脈打つような激痛で、前兆や吐き気を伴うことがあります。20~40歳代の女性に多く、月に数回、時には週に2~
3 回もの頻度で発作が起こります。月経も関係し、ピルも増悪因子の一つとされます。スマトリプタンという薬が有効です。
群発頭痛は前者と異なり20~30歳代の男性に多く2 ~3 か月間、ほぼ毎日、眼球をえぐり出したい程の激痛が襲い、その後1
~ 2 年間比較的無症状となりますが無症状期(寛解期)のない型もあります。多くは睡眠中に発作が起こり、アルコール摂取が大きな誘因です。予防薬も用いられますが急性期には酸素投与が有効です。
緊張型頭痛は頭が締め付けられるような痛みですが、前2 者よりも程度は軽く、男女差はありません。種々のストレスが誘因で肩や首筋のこりなどを伴う場合が多いためペインクリニックでは薬物治療とともに後頭神経ブロックや肩甲上神経ブロックなどをも併用します。
これらのほかに30~40歳代の女性に多い薬剤反跳性頭痛と呼ばれる頭痛があります。激しい頭痛のため、やむを得ず多種大量の鎮痛薬をご自分の判断で連用することが誘因です。薬ののみ方によってはさらにやっかいな“頭痛の種”が生じるという訳です。ご注意ください。
頭痛には脳外科的な病気や感染に伴うものがあり、また、緑内障の急性増悪、特発性三叉神経痛などとの鑑別も大切なので、まず確定診断を得ることが重要です。
平成14年2月 渡辺謙一郎
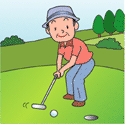 熱中症について
熱中症について
広く熱射病と俗称される熱中症のお話です。熱中症には通常①熱痙攣②熱虚脱③熱射病の3つに区分されます。
①熱痙攣は高温多湿の環境下で筋肉作業(労働、スポーツ)を行い多量の汗が出るにもかかわらず、水やお茶など電解質(塩分)を含まない水分の補給のみを行った場合に生じる、激しい痛みを伴う骨格筋の痙攣です。その本体は血液中のナトリウム濃度低下(低ナトリウム血症)で、電解質の補給により予防することができます。
②熱虚脱は高温多湿な環境下での持続的運動、作業や、高温多湿の室内(車を含め)への閉じ込めなどにより、体熱の発散ができない場合に生じます。この状態が進行すると、視床下部というところにある体温調節中枢に失調をきたし、体温はその後急上昇して、熱によるたんぱく質の変性や脱水により細胞障害、臓器障害を生じ、不幸なケースでは死亡したり、中枢神経障害を残すことになります。
20年ぐらい前からスポーツ時の水分、電解質補給の必要性が指摘され、現在ではごく当たり前のこととなっています。逆に近年では「ペットボトル症候群」と呼ばれるような持続的な多量の等分の取りすぎの害が見られ注意を要しますが、発汗時には適度な水分と電解質の補給を心がけましょう。また毎年のように車中へ放置された子供の死亡事故が報道されます。子供や高齢者は熱中症になりやすいことを肝に銘じ、ほんのちょっとの間車中で待っていてもらおうなどしないよう、買い物や行楽時などご注意ください。
13年6月 玉井晋吾
糖尿病は確実に増え続けている生活習慣病の代表です。厚生省の国民栄養調査による糖尿病(が強く疑われる)の方が360万人、糖尿病(が否定できない)予備軍の方が680万人であわせて1,300万人で、そのうち52.7%に肥満暦が見られた。
これは過去30年間におよそ30倍も増えたことになり今後もかなりのスピードで増え続けることが予想される。飽食の時代(コンビニ、外食産業やファーストフードの普及など食生活が欧米化)、1億人総グルメといわれて久しいが、国民一人当たりの総エネルギーは1970年代からあまり変わっていない(1日平均2,100キロカロリー)。摂取カロリーがそれほど変わってなくても消費カロリー、つまり活動(作業)エネルギーや運動エネルギーが減り、相対的に栄養過多(体格指数の上昇)となり、肥満をもたらしているものと思われる。その代表が車社会による運動不足である。
さらにテレビのリモコン化(寝ていながらにしてチャンネルが変えられ娯楽が楽しめる)、洗濯機の全自動化、エレベーター、エスカレーターなどが運動不足に拍車をかけている。情報化社会や経済優先の社会、ある意味での閉鎖社会は多くのストレスをもたらしている。過飲、過食、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣(環境因子)が糖尿病の引き金になっているのである。
平成12年10月 上原国光
1999年から新しい診断基準が次のように変わりました。①空腹時血糖値126mg/dl以上②随時血糖値200mg/dl以上③75g糖負荷試験で2時間値200mg/dl以上です。いずれかに当てはまる場合を「糖尿病型」と判断し、これに次の条件があれば「糖尿病」と診断します。①糖尿病に特徴的な症状(口渇,多飲、多尿、体重減少)②HGA1c(ヘモグロビンエーワンシー)6.5%以上③糖尿病家族歴がある④糖尿病歴がある場合です。
糖尿病はインスリン作用不足にもとづく慢性の高血糖が発生する代謝性の病気で、放置すれば網膜症による失明や腎不全などの重篤な合併症を引き起こします。インスリン作用不足はインスリン分泌低下をもたらす遺伝素因に、過食、過飲、運動不足、肥満、ストレスなど生活習慣の乱れを含む環境因子が加わって発症します。遺伝的素因を有する人が急に増えたとは考えにくいので、糖尿病の急増は高齢化に加え環境因子が大きな比重を占めていると思われます。したがって糖尿病の治療は不適切な生活習慣をいかに是正するかにかかっております。
糖尿病の治療は食事療法と運動療法が基本であり、補助療法として薬物療法があります。薬を飲んでいるので食事は少しおろそかにしてもいいと考えている方がいらっしゃいませんか?食事療法をきめ細かくやってこそ薬の効果があがります。良好なコントロールこそが三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)を予防し、天寿をまっとうすることができます。
平成12年11月 上原国光
糖尿病のコントロールの良し悪しはひとえに食事療法がうまく言っているかどうかにかかっております。簡単にチェックできるのは標準体重が維持できているかどうかです。病院などでコントロールの良否を判断するのに空腹時血糖や随時血糖が用いられます。最近では自己血糖測定器が普及し自分で測定する機会が増えつつあります。良好なコントロールは空腹時では120mg/dl以下、悪くても140以下、または随時血糖(来院時血糖で食後2時間が望ましい)は160以下、悪くても200以下になるよう努力しなければなりません。しかし、空腹時血糖や随時血糖は作為的に調節することができます。コントロールが悪くていつもお叱りを受けている方が、たまにはお褒めの言葉をかけてもらおうと思って前日から食事量を減らしたり、あるいは前夜絶食したりするとなるほど空腹時血糖や随時血糖は下がります。食事療法を守っているとほめてもらえるでしょうか。この涙ぐましい?までの過少申告はすぐに化けの皮がはがれます。ここにHGA1cと言う税務署員が登場し過少申告を見破りお褒めにらるどころか厳しいお叱り(追徴課税)を受けることになります。赤血球のヘモグロビンにブドウ糖が結合したもの をHGA1c(糖化ヘモグロビン)と呼んでおります。このHGA1cは血糖が高いほど、高血糖をきたしている時間が長いほど上昇します。この値は検査時からさかのぼって1~2ヵ月間の血糖コントロールの指標になっていて、2,3日食事療法を厳格に守ったからと言って簡単に下がるものではありません。正常値は4から6%です。
平成12年12月 上原国光
糖尿病性合併症には、糖尿病昏睡、呼吸器系や胆道系感染症、尿路感染症などの急性合併症がありますが、ここでは長年にわたるコントロール不良の結果起こる慢性合併症について述べます。慢性合併症は全身の臓器に起こりますが、特に細小血管障害として①糖尿病性網膜症②糖尿病性腎症③糖尿病性神経障害の三大合併症があります。また、大血管合併症として心臓、脳、手足などの太い血管に動脈硬化が起こり、心筋梗塞や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症の引き金になります。高血圧や高脂血症も高頻度に合併します。長期間にわたる持続する高血糖がなぜ重篤な合併症を引き起こすか、そのメカニズムについては諸説言われておりますがいまだ解明されておりません。動脈硬化の有無を調べる唯一の臓器は眼底(網膜)血管で、検眼鏡で見たり眼底撮影をすることで判断できます。網膜に血管に動脈瘤ができ、それが破裂して出血したり、白斑や静脈の変化、さらに新生血管が生じて硝子体出血を起こしたり網膜剥離を引き起こして失明にいたることもまれではありません。腎症では蛋白尿が持続して低蛋白血症や浮腫を生じ腎機能が低下して腎不全にいたり、透析を余儀なくされます。失明や人工透析の トップは糖尿病です。神経障害では手がしびれる、ジンジンする、こむらがえり、足の裏に何かひっついているような、夜間の自発痛などで不眠やうつ病の原因になります。常日頃から適正な生活習慣を実践することこそ合併症を予防する王道です。
平成13年2月 上原国光
1.低血糖発作とその予防
食事の遅れや摂取量が少ない場合、激しい運動後や薬の飲みすぎ、特にインスリンによる厳格なコントロールを行っている場合頻発します。血糖値が50mg/dl以下に下がりますと空腹感や脱力感、冷や汗、動機、手足の震え、さらに強い症状では頭痛、嘔吐、意識障害などを伴います。このような状態を低血糖発作と言います。この発作はいつどこで起こるかわからないので常に砂糖類を携行していなければなりません。万一、意識障害で経口摂取が困難な場合、かかりつけの病医院などを記入した糖尿病手帳を持っていると大変役に立ちます。
2.シックデイ(sick day)対策
風邪やインフルエンザで熱が出たり(感染症)、吐いたり、下痢をしたとき(胃腸症状)、また、けがや事故を起こした場合シックデイと呼びます。自分の守備範囲で適切な対応をすることをシックデイルールと言います。糖尿病昏睡や逆に重症低血糖を予防し、コントロールの乱れを防ぐのが目的です。尿糖,尿ケトン体、血糖を自分で検査できれば頻回にチェックしましょう。大切なことは経口血糖降下剤やインシュリン注射を中断しないことです。食欲がない、食事が取れない、嘔吐や下痢があっても勝手に治療を中断しないことです。
次に栄養、水分、ミネラル(食塩、カリウム)の補給を考えます。かゆ、葛湯、コンソメスープ、スポーツドリンク、みそ汁などで水分と塩分を補い、ジュース、果物などで糖質を補給します。なおかつ思わしくなければ早めに主治医にみてもらいましょう。
平成13年3月 上原国光
人間の体を構成する膨大な数の細胞は、栄養素を酸化させることで生きるためのエネルギーを保っています。つまり、細胞には、酸素の絶え間ない供給が必要なのです。
呼吸により肺に取り入れられた酸素は、ヘモグロビン(赤血球の中にある物質で、鉄と蛋白質でできている)と結合し、血液の流れを介して、全身の細胞に運ばれます。このヘモグロビンが減少している状態を「貧血」と言います。したがって、貧血になると、全身の組織や細胞は、酸素不足の状態になり、めまい、頭痛、疲れやすい、動悸、息切れといった症状が現れてきます。
貧血は、さまざまな原因でおこりますが、最も多いのが鉄欠乏性貧血です。今回は、この鉄欠乏性貧血について説明します。
鉄欠乏性貧血は、体内の鉄が不足することによって、鉄を主成分とするヘモグロビンの産生が不十分になるため起こる貧血です。この貧血は特に女性に多く、日本女性の8~10パーセントにみられます。鉄欠乏の原因には、偏食、胃切除後、消化管出血、月経による出血量が多いなどがあります。治療は、次の3つからなります。①鉄欠乏の原因となっている病気の治療②食事指導③鉄剤補給。
鉄欠乏性貧血の予防には、レバー、牛肉、大豆製品、貝類、海藻、緑黄色野菜などの鉄分の多い食品を取ることが大切です。しかし、いったん貧血になると、食事療法のみで改善させることは難しく、鉄剤の投与が必要となります。鉄欠乏性貧血は、鉄剤を服用することで治ります。
平成12年4月 壷内秀幸
現在私たち日本人は、4人に1人が癌で死亡しております。今回は、末期癌患者におけるターミナルケアについてお話をいたします。ターミナルとは終着駅、終点。ケアは心配、世話、用心の意味があります。
ターミナルケアとは、治療の見込みがなくなった、最後の3~6カ月の時期に於ける包括的なケアです。末期癌とは余命がだいたい3カ月以内で、治療は不可能です。転移を持つ進行癌で、肉体的ならびに精神的な苦痛を伴うものです。ターミナルケアの開始は、癌の治療から苦痛緩和へと移る分岐点であります。
癌末期医療の基本的な考え方は、死と向き合っている人に対して、その人が、その人らしく最後の人生を生きて貰うためには、痛みから解放してあげなければなりません。何故なら痛みは人間から、人間らしさを奪うものだからです。痛みがなければ、人間としてのプライドを持って生きていけます。このことは病人を1個の人間として遇する医学です。 誤解があるといけないので、あえて申しておきます。今までの医療が、病人を1個の人間として遇していないと言っているのではありません。死に向かって歩き続けている病人に対して、苦しみ、悩み、時には僻みもする弱い人間として、今まで以上に肉体と感情と魂を持つ1人の人間として接していく事が、とても大事だと申しているのです。
平成7年2月 小松 晃
今回は痛みそのものについてお話をします。痛みは(1)肉体的な痛み、(2)精神的な痛み、(3)社会的な痛み、(4)霊的な痛みがあります。肉体的な痛みは病気そのものによるものです。精神的な痛みは病気そのものに対する不安や死に対する恐れなどが痛みとなって出てきます。社会的な痛みは会社や家族内に於ける自分の比重の低下に対する不満や将来に対する不安、死後の家族に対する心配が痛みとなってあらわれます。霊的な痛みは、何か悪いことをしたから病気になったのではないかという宗教的な悩みです。痛みは以上の四つがないまぜになって出現する訳です。
これ等の事より単に病気だけを診てはなりません。肉体の痛みだけに目を向けてはなりません。病を持っている弱い人間、魂を持つ一人の人間として、いわゆる、全人的にみていかなければなりません。この複雑な痛みを持つ病人には真の人間として交わりを結ばなくてはなりません。可能な希望はかなえてあげましょう。こうした事がその人らしい死を迎えて頂くことが出来るのです。御家族、御友人、皆様に必要なことなのです。
原本平成7年3月 小松 晃
現在、末期癌のターミナルケアでは痛みが上手くコントロールできたら、そのターミナルケアは8割がた成功したと考えられております。それほど痛みというのは大きな問題なのです。
痛みを取る方法は色々ありますが、癌の激しい痛みを取る方法の一つとして、厳重な管理のもとに麻薬を使う方法があります。この痛みを取る方法の開発に一つの悲話があります。そのお話をしてみたいと思います。
英国の看護婦シシリー・ソンダースの恋人はポーランドの亡命貴族でした。楽しいはずの二人の生活は、彼の肺癌発病によって崩れました。痛みに苦しみながら彼は逝きました。死の床の中で彼は彼女に一つの願いを託しました。「医師になって、癌の痛みから解放する方法を見つけて欲しい。」恋人の死後、ソンダースは医師になり、末期癌の鎮痛に心を砕きました。1967年近代ホスピスの祖として、世界最初のホスピスである、セント・クリストファーズ・ホスピスを創設しました。ソンダース博士は末期癌の痛みのコントロールの重要な手段として麻薬を使用したのです。それは当時の英国の医学界の常識を越えた、大量の麻薬を使用して痛みのコントロールに成功しました。現在では、経口薬、坐薬として容易に使用されています。二人の非恋物語はこうして世界の福音となったのです。
平成7年4月 小松 晃
現在病院感染として注目を浴びているMRSAとは、メチリシンをはじめとする多くのベータ・ラクタム薬に耐性となった黄色ブドウ球菌のことで、メチシリン・レジスタント・スタフィロコッカス・アウレウスのMとRとSとAとを取ったものです。
ブドウ球菌は広く自然界に分布しています。人においても湿潤している場所や盲端を形成している場所によく定着します。会陰部、鼻腔、毛嚢などです。また、皮膚や粘膜にびらんが生じた際も同様です。褥創や耳漏、カテーテル挿入部位などがそれに相当します。
ブドウ球菌はコアグラーゼを産生する黄色ブドウ球菌と、その他の表皮ブドウ球菌をはじめとする多くの菌種に分けられます。皮膚や粘膜面から通常検出されるブドウ球菌は表皮ブドウ球菌で、病原性はきわめて少なく、同菌が常在細菌といわれる理由です。
一番重要なことは、MRSAが検出されたと言うだけでは、発症しているとはいわないことです。すなわち、検出されてもそのこと自体は問題ではなく、状態が悪く、抵抗力の弱っている患者さんに不幸にも感染して発症した場合に、難治性であることが問題です。一般の人々にとっては危険性が薄いことを知っておくのも必要です。
「MRSAは恐い菌か、恐くない菌か」という問題に対して、「恐い」と答えるとむやみと厳重な感染防止対策を考えようとするし、「恐くない」と答えるとまったく軽視されてしまいそうです。本来そういうことではなく、もっと医療の原点ともいうべき診療姿勢の問題といえます。
一部マスコミのやや偏向的で扇情的な報道に過度に反応することは良くないことです。MRSA発症者を出さないためには、MRSAが分離された患者さんとその家族の方々を含めた一般の人々と医療従事者とが、お互いに信頼し合いながら冷静な気持ちで協力して、適切な便覧に沿った感染防止対策を講ずることが肝要です。
平成6年5月 徳永常登
高血圧、糖尿病、講師血症などの成人病の原因の一つとして、近年インスリン抵抗性が注目されています。
インスリン抵抗性は、インスリンというホルモンの効果が発現し難い病態で、インスリン感受性の低下またはインスリン反応性の低下した状態です。
高血圧症、耐糖能異常、主に高中性脂肪血症および肥満はそれぞれに独立した異常ですが、いずれもインスリン抵抗性を基盤としたもので、これらの合併は“死の四重奏”と呼ばれ、冠動脈(心臓)疾患発症の好発条件となります。
インスリン抵抗性とそれによる代償性高インスリン血症(インスリンの効果が不十分なため反応的にインスリン分泌が増加する)では、高血圧、耐糖能異常、高中性脂肪血症、低HDLコレステロール血症などのいわゆる成人病と呼ばれる病態が重なりやすく、冠動脈疾患発症の危険性が高い症候群としてシンドロームXとかインスリン抵抗症候群とか呼ばれています。
代償性高インスリン血症の存在は糖代謝や脂質代謝に影響し、耐糖能低下の促進や中性脂肪の産生亢進およびHDLコレステロール産生低下など各種成人病の増悪要因となるばかりではなく、血圧の上昇作用を介して冠動脈疾患や脳血管疾患など動脈硬化性疾患発症の危険性を高める結果となります。
インスリン抵抗性の成因としては肥満、耐糖脳障害、肝疾患、感染症、内分泌疾患などの多くの病態で認められていますが、このうち成人健常者の最も重要で予防可能な成因は肥満と耐糖能障害であり、定期的な検診が重要かと思われます。
平成6年5月 武内 寛
リウマチは、正式には慢性関節リウマチと呼ばれ、全身の関節に痛みとはれを伴う慢性の病気です。男女比は1:3と女性に多く見られ、発病年齢は40歳代が一番多く、次いで30歳代、50歳代の順です。
リウマチの初期症状は、関節痛と関節のこわばりで、数週間から数ヶ月にかけて徐々に出現します。関節痛は始め手足の小関節に出現することが多く、進行すると膝や肩などの大関節が侵されます。リウマチに侵された関節は、増悪・軽快を繰り返しながら次第に進行し、最終的には変形が強くなり、関節の動きがほとんどなくなります。
このため日常生活に支障をきたし、ひどい場合には寝たきりになります。関節のこわばりは、朝の起床時のみに見られることが多く、症状が進行すれば一日中こわばりの続くこともあります。
リウマチの治療は、現在でも原因がはっきりしないため難治です。しかし、注射金剤を始め、数種類の抗リウマチ剤が開発され治療効果を上げています。
ですから、早期から専門的知識を持った医師のもとで、しんぼう強く治療を受ければリウマチの進行を予防し、ほぼ満足できる日常生活を送ることができます。
また、不幸にしてこれらの薬に反応せず、病勢が進行し、膝などの関節が強く侵されても、人工関節置換術などの外科的治療が進歩してきているので、寝たきりになる人は非常に減少してきています。
平成6年2月 本藤史郎
 暑さと体
暑さと体
真夏の太陽の下では、公園の鉄柵も、さわれないほど熱くなります。私達の体がそのようにならないのは、皮膚がクーラーの役目をしているからです。
その仕組みは汗腺からの水つまり汗の蒸発と、皮膚の血管の拡張による放熱です。したがって、急に熱くなり、このクーラーが、いきなりフル回転しますと、汗として水と塩分が失われ、また内臓へ送られるべき血液が減って変調が起きてきます。「夏ばて」です。 しかし、4日から7日くらい暑さに慣らしますと、水や塩分を調節するホルモン等も態勢を整えて、充分暑さに耐えられるようになります。
暑さになれていない人におき易い異常は、「熱けいれん」(こむらがえりのこと)です。足や腕、腹の筋肉におこることもあります。汗のため水と塩分が失われたためです。うすい塩水(1%500cc)をのめばなおります。
「日射病」: 熱い直射日光の下でよくおきます。顔色が悪くなり、めまいや失神がおきます。皮膚に血液が集まりすぎて、心臓がから回りするためです。涼しいところで横になればなおります。
「熱射病」: 前のものと違って、体温が40℃近く上がります。激しい運動中に足がふらついたり意識がぼんやりしてくると危険です。すぐに救急車をよぶことですが、その間もとにかく冷やすことです。運動前、運動中の水分補給が予防になります。その他、体温が41℃以上になる重いものもあります。
平成3年8月 西信弘夫
 超音波診断について
超音波診断について
近年、特に著しい進歩を遂げている診断法に超音波診断法があります。
超音波とは一般に耳には聞こえないほど高い周波数の音波をいいます。それを機械を用いて体内に入れ、体内の各臓器(肝臓、胆のう、すい臓、腎臓など)から跳ね返ってくる音の強さを画像としてとらえる方法が、超音波診断です。病院などで検査に用いる場合、次のような利点があります。
①無害で、検査を受ける方の苦痛がない。②各臓器の動きを観察しながら診断できる。③薬や注射はほとんどの場合使用しない。④検査結果がその場でわかる。⑤早期癌の診断も可能。
例えば、健康診断や人間ドックに超音波検査が普及してきたため腹痛がなく、血液検査などに異常のない方の中からも、胆石が発見されることが多くなっています。また、肝臓は、病気の部分があっても症状に現れることが少なく、良性悪性にかかわらず、血液検査などが必ずしも的中しないため、超音波検査が用いられるまでなかなか発見することができませんでした。これも最近は発見が多くなっています。
超音波診断は、このように多くの特徴を持っていますので、まだ受けておられない方にも、ぜひ受けられるようおすすめします。
平成2年4月 三宅川登
現在、ある程度の年令の方は大抵痛風という病気の話を聞いた事があると思います。この病気は、昔は日本では贅沢病とか、欧米では帝王病とか言われ、比較的稀な病気でしたが、戦後日本も経済的に豊かになり、食生活も急速に欧米化が進み、痛風は日常的な病気になってまいりました。
痛風とは血中の尿酸(蛋白質が体内で分解される時に出てくる終末産物の一つ)が増加(この状態を高尿酸血症と言う)して発病する疾患で、極めて特徴的な急性関節炎(急性発作)です。好発部位は足の親指のつけ根の部位であり、そのほか足首、膝、肘、手首などにも発症します。その痛みが激烈な時は発赤、腫れ、局所の発熱などに伴い、時には何日も痛みのため歩行困難は勿論、夜間に睡眠もできません。
この痛みの治療には以前はコルヒチンという薬が特効薬と言われて使用されてきましたが、痛風の原因である高尿酸血症の研究の進歩と共に、コルヒチンの副作用が注目され、最近は優秀な非ステロイド剤の合理的な使用法により比較的早期に痛風発作の疼痛から解放されるようになってきました。
しかし発作がおさまったら本人はつい油断をしがちです。高尿酸血症の結果として起きる痛風ですから、次は尿酸の代謝異常に対する治療が必要であります。
高尿酸血症は、身体の中に尿酸が過剰に溜まったために、血液中の尿酸の濃度が異常に増加した状態でその原因として、尿酸の産生過剰と、尿酸の排泄機能低下(体外に出す能力が弱った状態)及び両者が合併しているものとがあります。
疼痛発作の再発予防と共に、更に重要な事は、腎臓障害・尿酸結石・動脈硬化・心筋障害その他の重大な合併症の予防のためにも充分な注意が必要です。従って、高尿酸血症は立派な全身疾患である事が良く理解出来るでしょう。
痛風は男性特有の病気と言われておりましたが、女性の患者もまれにおり、また濃厚な遺伝性を持つとも言われていますので、そのような家系では特に注意が必要です。
以上の事をよく認識して主治医の指示に従って服薬と共に、食事療法と生活指導を守って下さい。
最後に食事療法の簡単な原則を述べます。
1.プリンを多量に含む食品、例えばイワシ、臓物、肉エキスを禁ず。2.脂肪の摂取は過量にならないようにする。3.糖質、蛋白質は適量、果物は過剰にならぬようにする。4.アルカリ性食品をとるようにする。5.心臓血管系の障害に注意しながら、水分の摂取量を充分にし、1日の尿量を2リットルく
らいにする。6.酒類はできるだけとらないようにするが、やむを得ない場合は、清酒1合、ビール1本又はウイスキー3分の1合いずれかにする。7.高カロリー食で肥満にならぬようにする。
以上簡単ですが、痛風についてお話しましたが、自分で病態を勝手に判断したり、色々の注意事項を忘れて油断をしないようにして、主治医の適切な指示に従って療養し、これから一層快適な生活をするように心掛けましょう。
平成元年11、12月 今治市医師会
正常の人では、血液中のブドウ糖の値は、大体、空腹時で70~110mg/dl、食後で140mg/dl以下位の狭い範囲に調節されています。
ところが、この血糖が何らかの原因で乱され、一般に180mg/dl以上になると尿中に糖が現れることになります。
糖尿病は、インスリンというホルモンの作用の不足によった血糖の上昇及び血糖の排出を一つの特徴とします。広く体全体の糖や脂肪や蛋白質などの代謝(体の構成成分を運んだり、組み立てたり、壊したり、エネルギーを貯えたり使ったりする仕組み)の病気であります。今日ではこれをⅠ型(若年型)Ⅱ型(成人型)、二次性(他の病気などの結果起こったもの)などに分類しています。
Ⅰ型は、主に子供と若い人に起こる重症の糖尿病で、急激に始まり、インスリンを注射によって補わなければ、急速に衰弱して、やがて昏睡死するタイプです。
二次性は、他の原因を見つけて治療することにより、多くはよくなります。
Ⅱ型は、遺伝的素質のある人に、食べ過ぎと運動不足などの良くない状態が続いた時、多くは中年以降に発病する、穏やかな糖尿病であります。ですから知らないうちに何年も経過する人が約半数を占め、その間に合併症が進むことになります。慢性合併症の主な原因は、血管が壊れることですから、その障害は全身に及び、しかも取り返しのつかない事になるまでほとんど気付かれないこともあるのは恐ろしい事です。
昭和62年3月 白石三思郎
糖尿病の慢性合併症は網膜症、(眼の奥の変化)、腎症、神経症、壊疽、脳血管障害(中気)、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)などで、特に網膜症、腎症、神経症については、他の病気とは明らかに区別される細い血管の障害が原因です。さらに脳血管障害や虚血性心疾患などの大きな血管の障害も進行します。
以前、日本では腎症が糖尿病患者さんの第一死因でしたが、最近では脳血管障害や虚血性心疾患が増加して来ています。
糖尿病が発症してから数年で、前記合併症が現れ始めます。
そのうち網膜症は、眼の奥が唯一、細い血管の変化が眼で見える場所で、しかも適切な時期に眼科的な処置を行う事により、進行を阻止できるので、早い時期に専門医による詳しい検査を受ける事が是非必要です。
腎症は、まず蛋白尿として気付かれ、重症になれば毒素も上昇し、特別の治療が必要となります。
神経症では、多くは軽いしびれ、痛みなどの症状で、手足先から始まり、次第に上向します。内臓に及びますと、立ち眩みで歩けない、激しい下痢、便秘の繰り返し、消化不良や男の人の性的不能などの症状が出て、なかなか治療に反応しません。
壊疽では、時には痛みもなく手足が腐る事があり、深爪、靴の圧迫などを避け、清潔にして予防し、インスリンによる治療を行えば多くは切断しなくてもよくなります。
脳血管障害や虚血性心疾患は、まず糖尿病に合併しやすい高血圧、肥満、高脂血症を改善して、予防するのが第一です。
以上、網膜症以外に対しては決定的な治療法がなく、その発症と進行を予防するには、自ら正しい知識を身につけ、努力して、栄養過多などによる体質悪化を改善して、注意深く糖尿病をコントロールするしかありません。現代の医学は、ただそれを手助けするだけしかありません。
昭和62年4月 白石三思郎
 エイズってなあに?これだけは知ってほしいこと
エイズってなあに?これだけは知ってほしいこと
エイズ患者は、1981年に米国で初めて発見されて以来、世界中でどんどん増え続けています。日本ではまだ患者数は少ないのですが、このままでは欧米に続いて増えて行くだろうと心配されています。
今までエイズになっているのは、男性同性愛者と薬物中毒者が大部分でしたが、異性間の性的接触でも発生しているのが現状です。
エイズの原因はウイルスです。エイズウイルスは非常にうつりにくいウイルスで特別の場合以外はうつりません。エイズウイルスは、体の抵抗力をつかさどる細胞(リンパ球)や脳の細胞に入り込んでその機能を破壊してしまいます。ウイルスが体の中にいるかどうかは、うつって8週間たてば血液検査でわかります。うつった人のうち、1~3割の人が数年の内に症状が出てくると言われています。症状は、発熱や下痢が続いたりしてやせてきます。病気が進んで体の抵抗力が落ちてくると色々な病気を起します。現在のところ特効薬はなく、発病すると3年で4人のうち3人が死亡しています。
エイズは傷ついた皮膚や粘膜にウイルスを持っている人の血液や精液がつく事でうつります。普通の生活の中ではうつりません。咳やくしゃみで空気を介してうつることもありませんし、握手などの日常的なお付き合いで移ることもありません。気を付けなくてはいけないのは、「性的接触」と「血液による汚染」だと言い切っても良いでしょう。不特定の相手(男女とも)との性的接触は避けましょう。エイズは心掛け次第で予防できる病気です。正しい知識があれば心配することはありません
エイズに関する相談や血液検査は保健所で受け付けています。
昭和62年5月 吉野俊昭
年をとると物忘れがひどくなり「大分ボケてきた」とか「耄禄した」とかよく申します。加齢と共に老化し、老化と共に現れる軽いボケは生理的現象として認められるもので病的なものとは言えないものであります。
老化によるボケは一般的に精神活動が低下した状態であります。知能低下の程度は軽く、普通の日常生活で重大な支障を来すことはありません。また、どんどん進行して悪くなることもありませんので、老化の当然の結果として、生理的範囲内であると受け止められています。
しかしボケはよくない状態であることに変わりありません。このボケが老年痴呆の始まりであることが多いので注意しなければならないと思います。
痴呆とは 一度熟成し、完成された脳組織が何らかの変化をうけて、病気になる前に持っていた知能が衰え、精神機能がゆっくりと少しづつ、持続的に低下し、だんだん悪くなって行き、逆もどりして良くならない状態を言います。
痴呆はいろんな病気でみられ、いくつかのまとまった症状を呈しますが、その中心は知能の低下であります。社会生活が妨げられたり職業的機能が果せない状態に知能が失われて初めて痴呆と言えるのであります。
知能の一部である記憶がなくなったり、記銘力が低下する事が痴呆の第一の条件であります。その他、思考力の低下、判断力の低下、計算力の低下、時間や場所の見当づけの異常、失言、失行、失認、人格の変化、感情の異常、気分の異常と言った症状が幾つか組み合わさって、知能の低下と一緒に出て参ります。
ボケは大体65歳頃から多くなり、70歳から75歳(2.6%)を越えると急に多くなり、85歳以上では4人に1人の割合になります。
ボケは寿命の延長、老人人口の増加と共に増加しています。
ボケを示す病気はたくさんありますが老化による老年痴呆と血管性の痴呆が痴呆を示す病気の大部分(8.7%)を占め、年寄りで最も多いのが、この二つの痴呆であります。
昭和60年6月 菅 勝男
65歳頃より脳の働きが衰えた結果起こってくる病気で、症状としては精神機能の低下と人格の崩れが中心であります。記憶力がおとろえ(新しいことを覚えられない、古いことも思い出せない)見当識が障害され(今何年何月か何時頃か、ここはどこか分からない)計算も不良(金の勘定が出来ない)判断力も不良(よくだまされる、是非善悪の弁別が出来ない)などの他、身だしなみがだらしなく、慎みがなくなり人格の崩れが認められます。さらに夜中に意識がもうろうとして、幻覚、妄想、興奮、不安を伴うことがあります。
少し具体的に述べてみます。物忘れがひどくなり、ものを置き忘れたことも忘れて平然としている。食事をしたことを忘れて「食べていない」という。受話器を置いた途端に電話の内容を一切忘れてしまう。ひどくなると家族の名前を忘れてしまう。字は忘れる、書き誤る、場所の見当が悪いのでよく道に迷い、外出すると家に帰れなくなる。時間の見当が悪く、夜中に目をさまし、わけの分からないことをわめいて歩きまわる。言葉が乱暴になり、その人らしさがなくなり、着物がきちんと着れない。トイレに行くと汚し、ご飯はこぼす。部屋に大小便をたらし、手に糞をつけて平気でいる。ボケの自覚、病識がなく、火をもてあそぶというような症状がいつとはなしに進み、だんだん目立つようになるのが老年痴呆の特徴で、大体数年後に廃人となり家庭生活が出来なくなります。
老人がボケてきた時にはこの病気ではないかと疑いが起きますが、多少の物忘れがあっても老年痴呆とは限りません。この病気を疑わせるのは重大なことを忘れ、忘れたことを自覚しないことです。忘れやすいことを気にしている間は真のボケではありません。知能だけでなく、だらしなく、慎みがなく、恥ずかしいことを平気でしたり、言ったり、ゲラゲラ笑って出歩く様になると、これは人格が崩れはじめたと考えねばなりません。又、物を置き忘れて盗まれたと騒いだり、汚いことに無頓着になったり、終日食べて居眠りしている時には疑いが強くなりますので注意していなければならない症状です。
昭和60年7月 菅 勝男
老年性痴呆の3分の1以上が脳血管性の物で、老年痴呆よりも多く、一番多いものです。55歳から65歳頃に始まることが多く、男性に多いと言われています。
脳の働きには栄養が必要ですがその栄養を届けるのは血液で、血液を運ぶ道路の役目をしているのが血管であります。年をとると脳血管が老化して狭くなったり、つまったり、破れたりしますので栄養が充分行かなくなり、脳の働きが衰えて痴呆を生じます。この血管性痴呆も老年性痴呆と症状は大差はないのですが、幾分ちがったところがあります。この血管性のボケは初めはボケ症状でなく、ごくありふれた身体症状で始まります。
頭重、頭痛、頭がすっきりしない、特に後頭部がうっとおしい、肩こり、めまい、のぼせ、耳鳴り、立ちくらみ、いらいら、怒りやすく涙もろくなり、寝つきはよいのに眠りが中断して目がさめる、物忘れ、度忘れが多くなり、根気が続かなくなるといった症状が出て参ります。
約半数の血管ボケは、脳動脈硬化症、脳血栓、脳出血発作後に急激に起こります。ですから高血圧、動脈硬化症の人に多く認められます。血管ボケの特徴は症状が良くなったり悪くなったり、一進一退しながら階段状に急に悪くなり、しばらくしてまた急に悪化するような進み方をします。そして、次第に知能の低下や人格の変化がはっきりしてきて、高度のボケの状態になります。しかし、最も特徴的なことは、物忘れはひどくなりますが、人格のくずれは比較的軽く、その人らしい情操や品格をあまり失っていません。道徳観念も低下せず、記憶の衰えでも何もかも忘れるのではなく、所々に高級な知識や判断力をもっていまして、盲も働きがざるの目の様に脱落したという感じを受けます。その他大したことでないのに泣いたり、激怒したりする感情失禁の症状が出てきます。ぼんやりして幻覚、妄想を起こし、夜間せん妄、運動マヒ、言語の異常、痙攣などがみられます。この血管性痴呆の原因は動脈硬化ですから、それを予防し、循環障害を改善する様にしなければなりません。また、脳卒中発作後に起こりやすいのですから、再発を防ぐことが大切であります。
昭和60年8月 菅 勝男
Copyright(C)1998